「すみません、ちょっとお話があります」
デスクに呼ばれて聞かされたのは、まさかの退職願。しかも1か月後。
心当たりがない…と思っても、実際にはその数か月前から予兆は出ていることがほとんどです。
僕も過去に何度も「急な退職」に遭遇しましたが、後から振り返ると必ずサインがありました。
この記事では、部下が辞める前に見せる兆しと、上司が今から準備できる5つのことを、実例つきでお伝えします。
1. 日々の表情と会話量の変化を記録する
ありがちなサイン
- 雑談が減る
- ミーティング中の発言が短くなる
- アイコンタクトが減る
失敗例A:忙しさにかまけて「最近静かだな」と思いつつ放置。2か月後に退職表明。
失敗例B:月1面談のみで状況を把握。日常の変化に気づけず、後から「もっと早く声をかければ」と後悔。
成功例:毎朝1〜2分の軽い会話でコンディションを把握。変化を感じたら即フォロー面談を設定。
回避策ToDo
- 朝礼や挨拶時に声のトーン・表情をチェック
- SlackやTeamsの発言頻度も記録
- 変化を感じたら48時間以内に5分面談
2. 業務量と負荷を定期的に棚卸しする
退職理由のトップは「業務過多と不公平感」。
特に中堅層は“仕事ができる”がゆえに業務が集中し、燃え尽きやすい。
失敗例A:仕事が早い部下に案件を回し続け、半年で疲弊→退職。
失敗例B:繁忙期の残業時間を把握せず、気づけば月60時間超。
成功例:四半期ごとに案件量・残業時間・負荷感を棚卸し。本人にも状況を共有し、優先度調整やサポートを実施。
回避策ToDo
- 月1回、業務量チェックシートで自己申告
- 残業時間40時間超は必ず面談
- 案件の偏りはチームで再配分
3. キャリアの方向性をすり合わせる
方向性がズレたままでは、いくら待遇改善しても離職は防げません。
失敗例A:「3年後はマネージャーに」と考えていたが、本人は「専門職を極めたい」派でギャップ大。
失敗例B:評価面談が形式的で、本人のやりたいことを掘り下げない。
成功例:半年ごとにキャリア希望シートを更新し、短期・中期・長期の方向性を確認。
ズレがあれば配置や役割を調整。
回避策ToDo
- 半年に1回のキャリア面談(短期目標・中期計画・望むスキル)
- 希望と業務の接点を具体的な案件で作る
- キャリアプランはチーム共有OK部分と非公開部分を分けて管理
4. 成果と努力を可視化してフィードバック
成果を出しても、評価されなければモチベーションは下がります。
特に中堅層は「影の努力」が多く、それが見えないまま埋もれがち。
失敗例A:成果物だけを評価し、過程を認めない→「やっても無駄」と感じ退職。
失敗例B:褒めるのが年1回の評価面談だけ。
成功例:週1で**「良かった点3つ」**を即時フィードバック。
Slackでも「#good-job」チャンネルを運営し、互いの貢献を見える化。
回避策ToDo
- 週1回、行動ベースの称賛フィードバック
- 月末に「今月のチーム貢献TOP3」を共有
- 成果物とプロセスを同じ比重で評価
5. 離職の“地雷”を減らす
人間関係・不公平感・放置感――これらは退職理由の常連です。
根本対策には「定期的な小さな改善」の積み重ねが効きます。
失敗例A:上司同士の対立に巻き込まれ、部下が板挟み→退職。
失敗例B:一部メンバーにだけ情報共有がなく、不信感が増大。
成功例:月1回のチームミーティングで課題を洗い出し、改善案を即実行。
情報は全員に同時共有し、“置いてけぼり感”を防止。
回避策ToDo
- 月1回、課題と改善案を匿名で回収
- 重要情報は同時に全員へ通知
- 人間関係トラブルは72時間以内に介入
実際に見たケース
- 突然辞めたAさん:表情の変化を放置→退職理由は「限界でした」
- 救えたBさん:負荷過多を棚卸し→案件を半分に→続投決定
- 離れたCさん:キャリアの方向性不一致で外資へ転職
- 残ったDさん:フィードバックを増やし、昇進後も継続勤務
90日アクションプラン
Day 0–30:可視化と傾聴
- 挨拶時の表情・発言を記録
- 全員と5分ヒアリング(負荷感・気になること)
Day 31–60:負荷調整と方向性確認
- 業務量を再配分
- キャリア面談で短期・中期の希望をすり合わせ
Day 61–90:成果承認と改善サイクル化
- 週1フィードバック+月末TOP3共有
- 匿名課題箱で改善案を即実行
まとめチェックリスト
- 表情・発言の変化を日々見ている
- 業務量を定期的に棚卸ししている
- キャリア方向性を半年ごとに確認
- 成果と努力を即時承認している
- 離職の地雷を小さく潰している
Q&A
Q. 退職を防ぐには給料アップが一番?
A. 給与だけで防げるのは一時的。キャリア・人間関係・負荷の改善とセットで考えるべきです。
Q. 忙しくて日々の観察ができない
A. 30秒でいいので挨拶+一言会話を習慣化。それだけでも兆しは見えます。
Q. 離職率が高い部署に異動してきた場合は?
A. 最初の1か月で全員とヒアリングし、原因と改善策をセットで経営層に提案しましょう。
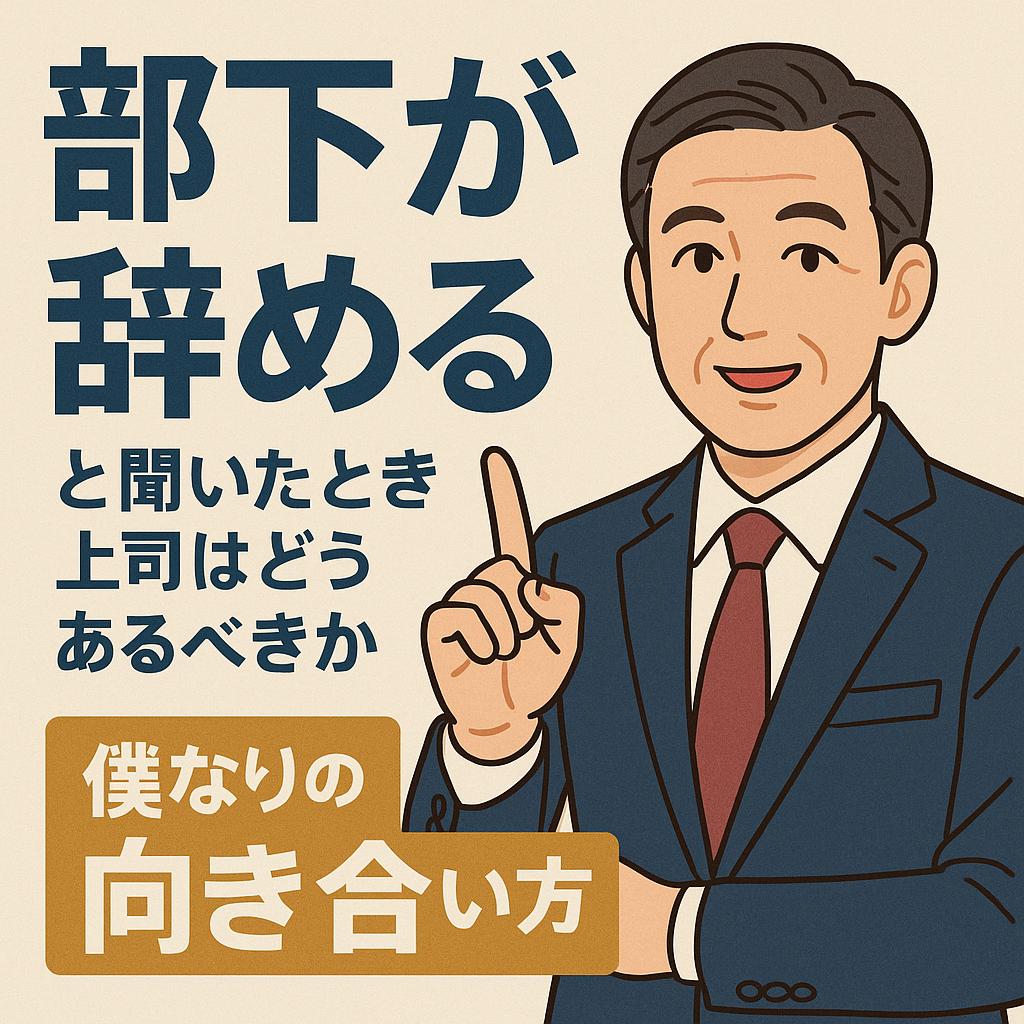


コメント