「自分には何の仕事が向いているんだろう?」
大学生の頃の僕は、そんな問いの答えがわからないまま、なんとなく“安定してそうな”大企業に就職しました。
特別やりたいことがあったわけでもなく、世の中の職種や業界のことも、恥ずかしながらほとんど知りませんでした。というか、分かろうともしてなかった。ダメ大学生ですね苦笑
そして今、40代になって、複数の業界・職種を経験した僕が思うのは──
**「あの頃、もっと“働くということ”の全体像を知っていたら、選び方も違ったかもしれないな」**ということです。
今日は、そんな後悔と気づきを込めて、「社会人にはどんな仕事があるのか?」というテーマを、就活前の大学生に向けて書いてみたいと思います。
■仕事を選ぶときの3つの軸:業界、職種、会社
まず、就職活動で混乱しがちなのが、**「業界」「職種」「会社」**の区別です。
この3つは、それぞれ違う視点の“選び方”になります。
| 軸 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 業界 | どんな分野の市場か | 通信、金融、教育、メーカー、小売、ITなど |
| 職種 | どんな仕事の中身か | 営業、開発、人事、経理、企画法務、総務、経営企画、ITなど |
| 会社 | どんなカルチャー・規模か | 大企業、中小、ベンチャー、外資など |
つまり、**「IT業界の営業職として、ベンチャー企業で働く」**というように、3つの軸を組み合わせて考える必要があります。
■職種は“ずっと一本”じゃない。キャリアは“積み上げ型”でいい
学生のときって、「一度選んだ職種で一生やっていく」と思いがちです。というか、具体的に会社に入ったことないので、想像できないのが普通だと思います。(優秀層は考えているかもしれませんが・・・)
でも実際は、営業から企画に異動したり、開発からマネジメントに転身したり、キャリアの中で職種が変わることは珍しくありません。僕自身、営業、商品企画、経営企画、財務、IR…と複数の職種を経験してきました。
むしろ、**「違う職種を経験したからこそ、全体が見えるようになる」**という面も大きいです。
たとえば、営業を経験している企画職の人は「現場感」があるし、経理を知っている営業マンは「数字に強い」。また、相手側の事情や気持ちが分かるようになる、という面もかなり重要だと思います。
なので、「職種を選びきれない…」と悩む必要はありません。
最初は“仮置き”くらいの気持ちでいいんです。
■よくある“勘違いあるある”をぶっ壊す
就活生や若手社員と話していて、「それ、ちょっと誤解だよ」と思うことがあります。例えば:
- 営業=つまらない/泥臭い → NO!
顧客と対話する“ビジネスの最前線”。人によっては企画職より面白い。一番人間臭いかも。 - 企画=華やか/かっこいい → NO!
実態は泥臭い調整業務や資料作りの毎日。数字との格闘も多い。経営企画とかM&Aでもやっていれば派手っぽいかもしれませんが、実際は経営と現場、経営陣同士、部署と部署など調整につぐ調整、Excelやパワポと格闘しながら資料作成、議事録作成など、、、実はかなりの割合が地味な仕事です。 - 大企業=安定 → NO!
会社が潰れなくても、自分のポジションが“安泰”とは限らない。最近パナソニックのリストラが行われていますが、業績が黒字でも早期退職発動が当たり前の時代になってきています。
結局、「職種のラベル」ではなく、「どんな環境で、どんな人と働くか」が一番大事だったりします。
■40代の部長が今、大学生に戻れるなら…
もし僕がもう一度、大学生に戻って就活をやり直せるとしたら、こう考えます。
- “知る”ことから逃げない
→ どんな職種・業界があるかを、ちゃんと調べる。偏見を捨てて知る。 - 最初から“正解”を探さない
→ 仮説ベースでいい。やりながらズレたら修正すればいい。 - “人”と“文化”をよく見る
→ 仕事内容より、「この人たちと働けるかどうか」の方が大事。 - 何が自分にとって一番大事か考える
→ 結局これを考えていないと、社会人になってから色々な葛藤に苦しむことになる。
■結論:キャリアは“修正可能な旅”です
人生は長いです。最初に選んだ職種や会社が、ずっと“正解”であり続けるとは限りません。
でも逆に言えば、どんな選択をしても、それを活かして別の道に広げることはできる。
僕自身がそうだったように、転職も含めてキャリアは“積み上げ型”でいいんです。
最初の一歩に、必要以上に怯えすぎないでください。
この世界には、あなたがまだ知らない面白い仕事が、たくさんあります。
ただし、前の記事でも書きましたが、”自分のストーリー”は常に考え続けて、自分なりの背景をもちつつ様々な選択肢から選んでいくことが大事だと思っています。
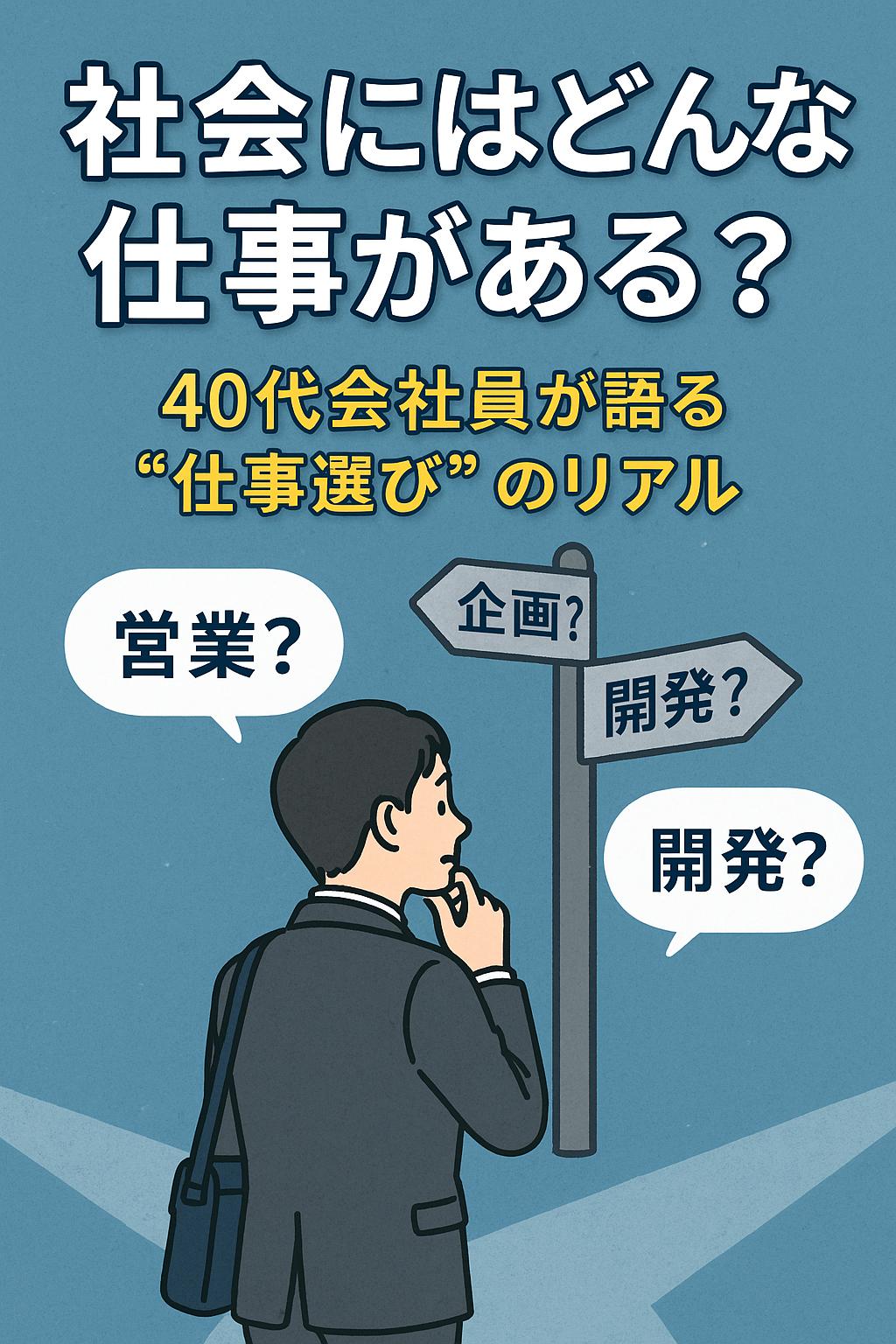


コメント