娘にPASMO(オートチャージ付き)を持たせることにしました
うちの娘は、小学生。
とはいえ、電車で行く習い事がいくつかあって、放課後の移動がなかなか大変です。
最初の頃は、小銭を持たせて改札前の券売機でチャージしていたんですが…
これ、親も子もけっこう面倒なんです。
子どもは「いくら入ってるか」なんて把握してないし、こっちも毎回チャージ残高を気にするのもなぁ…と。
そこで我が家がたどり着いたのが、
**「小児用PASMO+オートチャージ」**という選択。
しかも、今はスマホをGPS代わりに持たせているので、「モバイルPASMOでいいか」とも考えたんですが、ここにちょっとした落とし穴がありました。
モバイルPASMOは「小児+オートチャージ」に非対応だった
モバイルPASMOって便利ですよね。
iPhoneやAndroidでアプリからチャージもできるし、物理カードを持たせるよりも安心かな、と。
ただ、調べてみたところ…
モバイルPASMOは「小児運賃+オートチャージ」には非対応。
「なんだと…!」って思いました(笑)
つまり、小学生でPASMOを使いたい場合は、モバイルではなく“実カード”が必要なんです。
というわけで、やや回り道をしつつも、うちは「小児用PASMOの実カード」にオートチャージをつける方法を選びました。
導入までの流れはこうでした
PASMOにオートチャージをつけるには、特定のクレジットカードが必要です。
我が家が調べた限り、小児用PASMOでもオートチャージに対応しているのは「東急カード(TOKYU CARD)」だけ。
やったこと(順番)
- 保護者名義で「TOKYU CARD」を申し込み
- 娘用に「小児用記名PASMO」を作成(駅の窓口で可能)
- 東急カードの「ジュニアオートチャージサービス」に申し込み
- 数週間後にハガキが届く
- 指定の駅(東急線の有人改札)でオートチャージを設定
- 完了!
地味に**「駅に行って設定しなきゃいけない」**のがネックですが、一度やってしまえばあとはラクです。
実際に使ってみて感じた「5つのメリット」
PASMO+オートチャージ、思った以上に便利でした。
我が家で感じたメリットを5つ紹介します。
① チャージ忘れゼロ。安心して送り出せる
自動で一定残高を下回るとチャージされるので、「残高大丈夫かな…」という不安がなくなりました。
電車の改札で詰まる心配もナシ。
② 緊急時のお守り代わりになる
一定金額が常に入っている=何かあった時に「とりあえず帰ってこれる」「コンビニで水が買える」
親としては、これはかなり心強い。
③ コンビニ利用もOK。ちょっとした買い物に便利
習い事の前におにぎりや飲み物を買うとき、PASMOでピッと済ませられる。
子どもにとっても、“自分で買い物をする”という経験になっています。
④ 利用履歴がネットで見られる
親の東急カードと紐付いているので、PASMOの利用履歴はWebで確認できます。
「何に使った?」「どこ行った?」を、あとから一緒に確認できます。
⑤ 金銭教育のきっかけにもなる
「チャージ=お金が湧いてくる」ではないこと(笑)
オートチャージであっても、“お金の流れ”を見せておくと、お金の価値やルールの話が自然とできました。
懸念点と、それへの対策
もちろん、いいことばかりではありません。
実際にやってみて感じた懸念点と、その対策もまとめておきます。
◆ 落としたらどうする?
→ 駅の事務所ですぐに利用停止+再発行の手続きが可能(記名式PASMOだからできる)。
→ 定期入れに連絡先シールを貼っておく、ひも付きのカードケースを使う、などの対策をしています。
◆ 勝手に使いすぎたら?
→ コンビニ利用に関しては「いくらまで/どんなものならOK」というルールを明確にしてます。
→ 利用履歴を定期的に一緒に見るのも◎
◆ クレカ引き落としが不安?
→ 東急カードの明細を家計アプリに連携しておくと、PASMO利用分が可視化されて管理しやすいです。
まとめ:小学生にオートチャージPASMO、うちはアリでした
PASMOにオートチャージ機能をつけてみて、親の安心感と子どもの自立の両方が得られたように思います。
特に、都市部で電車移動が多い家庭や、送迎が難しい共働き家庭にはおすすめです。
もちろん、現金の管理も大切だけど、今の時代は**「電子マネーをどう使うか」を学ぶことも金銭教育の一部**。
我が家はこれからも、親子で相談しながらちょうどいい使い方を見つけていきたいと思います。
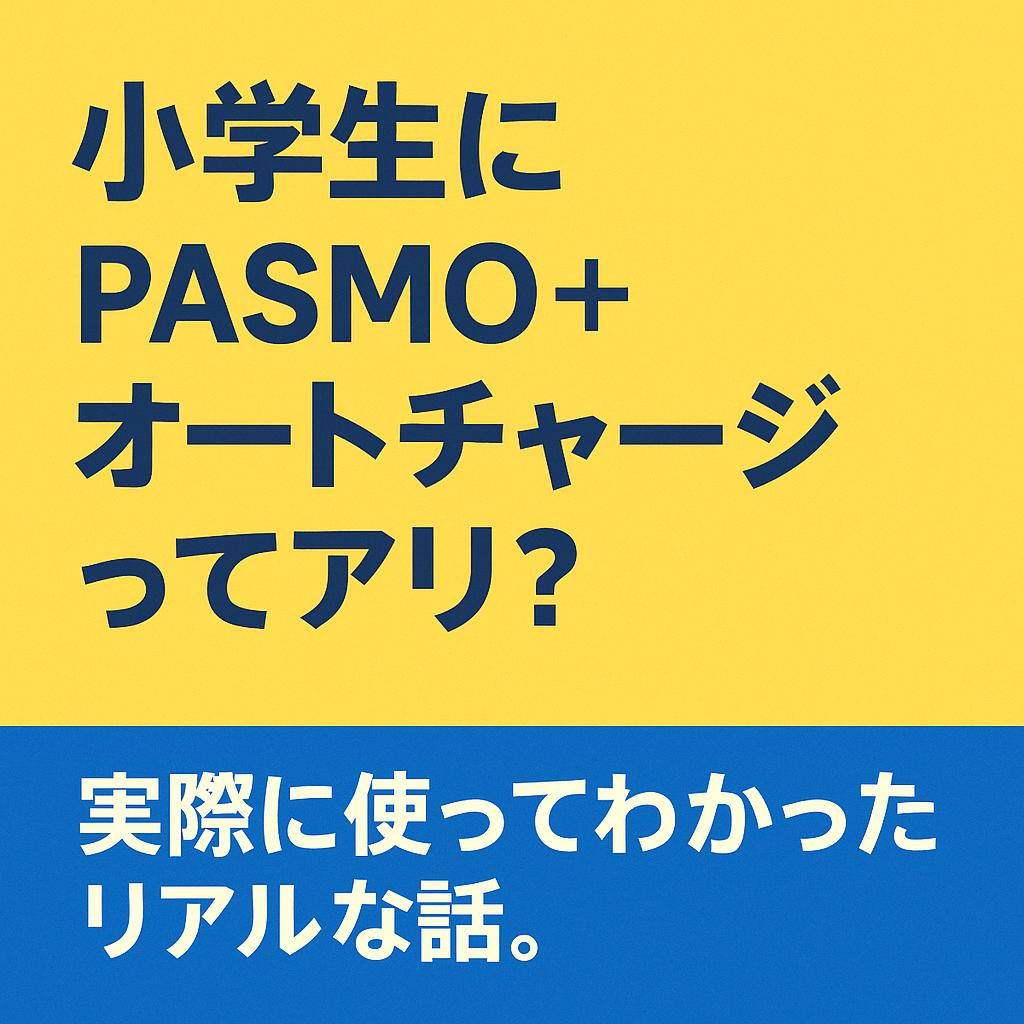

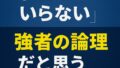
コメント