はじめに
最近、ChatGPTやCopilotといった生成AIを使う人が一気に増えました。僕自身も、副業のブログ執筆や勉強にAIをよく使っています。記事の下書きやアイデア出しにAIを使うと、本当に作業がはかどるんですよね。
ただ、ふとしたときに気になるのが 「これ、個人情報を入力して大丈夫なのかな?」 という点です。
便利さに甘えてつい名前や住所を入れてしまったり、会社の資料をそのまま貼り付けてしまったり…。でも後から冷静になると「これって情報漏えいにならないの?」と不安になった経験、僕自身あります。
そこで今回は、副業パパの目線で AIに個人情報を入れるときの注意点 を整理してみました。
AIに個人情報を入力して大丈夫?
結論から言うと、大事な個人情報は基本的に入力しない方が安全 です。
多くのAIサービスは「入力した内容を学習や品質改善に利用する場合がある」と利用規約に書かれています。つまり、うっかり入力した情報が将来的にAIの学習に使われ、意図せず外部に出てしまうリスクがゼロではないということです。
たとえばChatGPT(OpenAIのサービス)では、入力データが学習に活用される可能性があります。一方で、MicrosoftのAzure OpenAIや法人向けAIサービス「Safe AI Gateway」といったサービスでは「学習には使われず、自社のクラウド内で完結する」という形もあります。(ただし、これらは法人利用が前提)
要は、同じAIでもサービスによってデータの扱いはまったく違う んです。
AI利用で注意すべき3つのポイント
① 個人情報は極力入れない
氏名、住所、電話番号、マイナンバー、クレジットカード情報…。これらは言うまでもなくNGです。
副業や勉強でAIを使う分には「公開されても困らない情報」だけを入力するのが鉄則です。
例えば「埼玉県在住の40代男性」という程度の情報なら問題ありませんが、「埼玉県●●区XX○丁目○番地の山田太郎」と書いてしまったらアウトです。
入力前に「もしこれが外に漏れたら困るか?」と考えるだけで、かなりリスクは減らせます。
② 会社や顧客のデータは使わない
これは副業サラリーマンやフリーランスに特に重要なポイントです。(当たり前ですが)
会社の資料や顧客リストをそのままAIに入力するのは、第三者提供にあたる可能性 が高いです。個人情報保護法や守秘義務違反に問われるリスクもあります。それ以前に、会社の情報を業務外で使ったらアウトですが・・・
実際、社内で「ChatGPT禁止!」と通達を出している企業も少なくありません。もし業務でAIを使う場合は、必ず社内ルールを確認してからにしましょう。
③ サービスごとのデータ取り扱いを知っておく
AIと一口にいっても、サービスごとにデータの扱いはバラバラです。
(以下例示)
- ChatGPT(無料/有料プラン)
→入力が学習に使われる場合がある。履歴も残る。ただし、学習に使われないように
設定を変えることができる。(オプトアウト) - Azure OpenAI(企業向け)
→データは自社クラウド内で完結、学習に使われない。 - Safe AI Gateway(国内サービス)
→入力が外部に流れず、セキュアに利用可能。
要するに、「同じGPTでも裏側の契約次第でリスクが全然違う」ということです。
一般ユーザーが守るべき“線引き”
じゃあ、僕たち一般ユーザーはどうやってAIを安全に使えばいいのか?
答えはシンプルで、「公開されても困らない情報だけ入れる」 ことです。
✅ OKな使い方
- 英作文の添削
- レシピ相談
- 勉強の質問
- ブログ記事の構成を考えてもらう
❌ NGな使い方
- 源泉徴収票をアップロードして確定申告してもらう
- 健康診断書の内容をそのまま入力する
- 子どもの学校名や住所を入力する
僕自身も「これはAIに任せたい」と思ったとき、一呼吸おいて「これがもし誰かに見られても大丈夫か?」と自問するようにしています。
まとめ
AIは間違いなく便利で強力なツールです。でも、「AIはゴミ箱じゃない」という意識が大切です。
- 個人情報は入力しない
- 会社や顧客のデータは避ける(業務内でも業務外でも。業務の場合は会社のルールに従う)
- サービスごとのデータ扱いを理解する
この3つを押さえるだけで、安心して副業や勉強にAIを活用できます。
僕自身も副業パパとして時間が限られる中、AIの力にだいぶ助けられています。だからこそ、正しく安全に使っていきたいですね。
👉 今日からでもできるのは「入力前のひと呼吸」。
それだけでリスクはグッと減ります。ぜひみなさんもAIを味方につけて、副業や日常をもっとラクに、もっと楽しくしていきましょう!

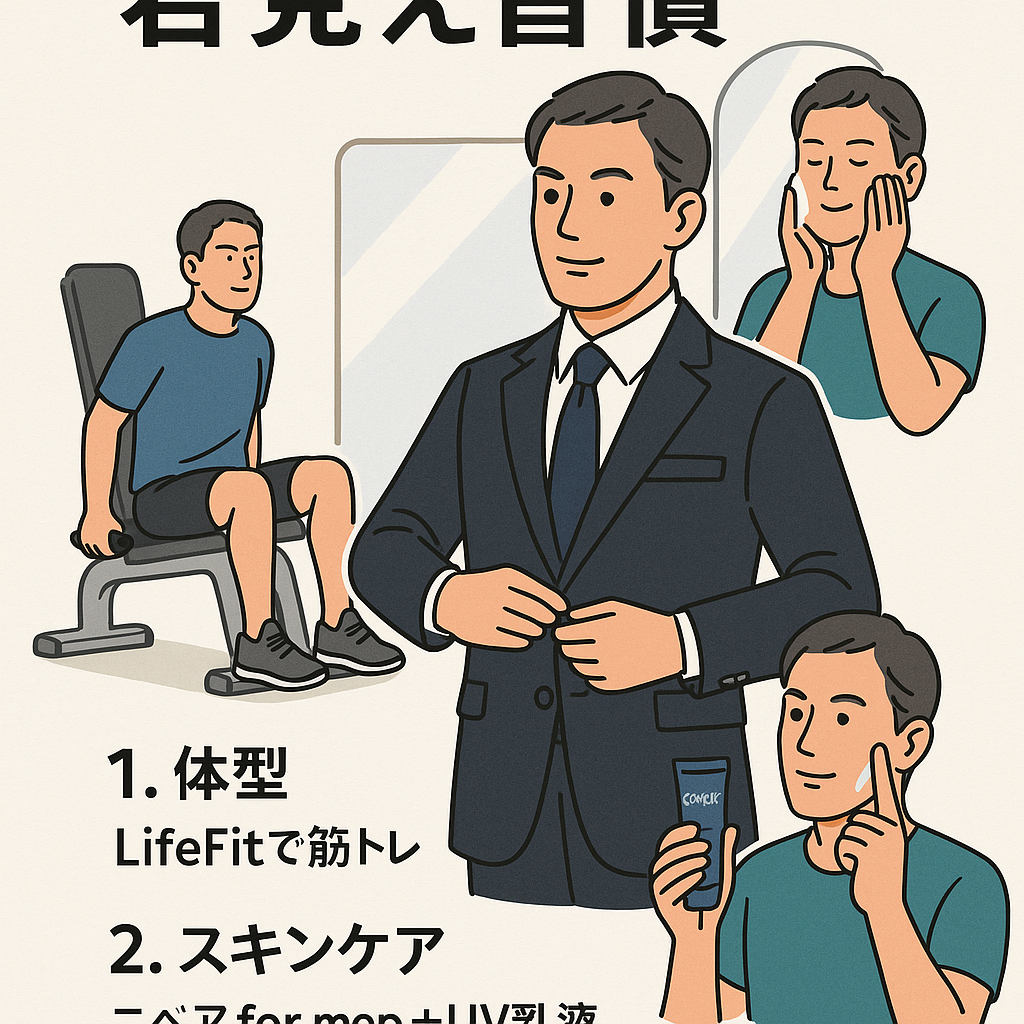

コメント