部長職と聞くと、「ある程度成功した会社員」として見られることが多い。でも、実際にはそう単純じゃない。
僕は中堅企業の部長職として働いているが、周囲や自分自身を見ていて感じるのは、「出世しても幸せじゃない人」には、共通するパターンがあるということ。
今回はそんなリアルを、本音でまとめてみたい。
① 生き残ることが目的になっている人
出世の結果、社内での立場を守ることが最優先になってしまう人がいる。
事業をどうしたいとか、会社を良くしたいという視点よりも、「とにかく自分の居場所を守りたい」というモードになっている。
そういう人は、いわゆる「イエスマン」「コバンザメ」と言われがち。周囲からの信頼も得づらく、結果として本当の意味での幸せにはなりにくい。
② 経営と部下の板挟みになる
部長になると、経営層と対峙する場面が増える。
時には、明らかに無理筋な方針や数字を押し付けられることもある。一方で、現場の部下からは「なんとかしてくれ」と突き上げを食らい、退職者が出ることも。
板挟みの中で心がすり減り、「自分は何のためにここにいるのか」と感じてしまう瞬間がある。
③ 居場所がいなくなるリスクがある
これは以前も書いたが、部長職というのは“替えがきかない”と思われがちな分、経営者が変わると真っ先に狙われるポジションでもある。
新しい社長が、自分の信頼する外部人材を連れてくれば、自分の居場所は突然なくなる。
「まさか自分が?」と思っていた人が、あっという間に外される。そんな現場を何度も見てきた。
④ さらなる出世が近いようで遠い
部長は、役員に最も近いポジションのひとつだ。でも実際には、そこからが遠い。
理由はシンプル。
- 圧倒的に分かりやすい実績
- 社内政治力やキーパーソンとの関係性
この2つがなければ、昇進は難しい。
プレーヤー時代のように「がんばった」「数字を作った」だけではもう届かない世界。そこに気づいたとき、多くの人が落胆する。
⑤ 思ったほど給料は上がらない(が、大きな“段差”が待っている)
「部長になれば年収がグッと上がる」と思われがちだが、中堅企業ではそこまで劇的な変化がないケースも多い。
しかも、厄介なのはこのあと。
多くの企業では、“部長”と“執行役員”の間、あるいは“執行役員”と“取締役”の間で、報酬に大きな段差が存在する。
その段差を超えられる人はほんの一部。
つまり「出世はしたが、報酬的には頭打ち」という状況に陥りやすく、そこに虚しさを感じる人も少なくない。
まとめ:「出世=幸せ」じゃない。でも、それでもやる意味はある
この記事では、あえて“幸せじゃない”側面を書いてきた。
でも誤解しないでほしい。
出世すること自体が悪いわけじゃない。
むしろ、そこに意味を見出せる人にとっては、やりがいのある仕事でもある。
例えば、その部署を大きく変えて、より働きやすく、パフォーマンスが出る職場に変えることもできる。また、人材育成の喜びを感じることもできる。
大事なのは、「何のためにその役職を目指すのか」「そのポジションで何をしたいのか」という軸を持っていること。
そうでなければ、出世してもモヤモヤは消えない。
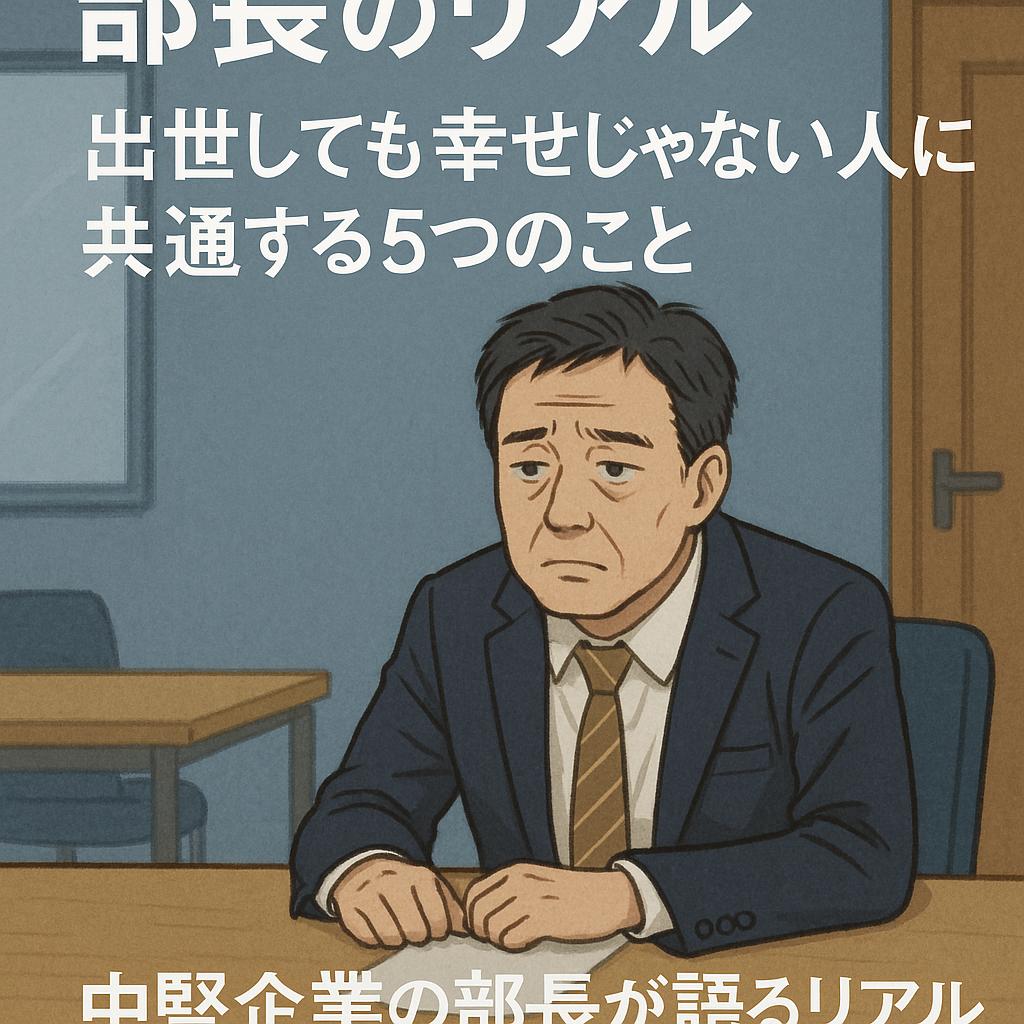


コメント