40代で管理職として転職――経験も肩書きもあるし、きっと大丈夫。そう思って入社したのに、数か月後には会議で発言が減り、プロジェクトから外れ、気づけば「最近あの人見ないね」という空気に。僕はこれまで複数の会社で、入社半年〜1年で静かにフェードアウトしていく40代管理職を何人も見てきました。
原因は才能不足ではありません。多くは、**新しい環境に合わせる「最初の立ち回り」**を誤っただけ。この記事では、実際に見聞きしたケースをベースに、消えていく人の特徴5つと、同じ轍を踏まないための回避策をまとめます。自分のことだ…と感じたところからでいいので、ひとつずつ直していきましょう。
1. 前職のやり方に固執する
ありがちなセリフ
「前の会社ではこのフローで回ってた」
「このやり方が業界の常識だから」
最初は“善意の助言”のつもりでも、繰り返すほどに現場の自己否定に聞こえます。前職で勝てた方法は、今の会社の規模・顧客・人材・ルールでは噛み合わないことが多い。
失敗例A:入社2週目で前職のKPI運用を持ち込み、会議を“講義”にしてしまう。現場が白け、根回しもなく提案は棚上げ。
失敗例B:「これ、昔の部下にはウケたんだけど」と成功談を重ね、気づけば「前職の話しかしない人」扱い。
成功例:最初の3か月は現行フローを観察→言語化。現場の困りごとを一緒に拾い、「小さなABテスト」を提案。半年後に“現場が勝つ”形で標準化。
回避策ToDo
- 最初の90日は比較より観察。差分はノートに溜めるだけにする
- 提案は小さく・検証付き。数字で“現場が得する”ことを示す
- 「前職では」は月1回まで(自分ルール化)
2. 部下との距離感を間違える
年下部下に対して、上から“型”を押しつけるか、逆に気を遣いすぎて指示が曖昧になるか――どちらも地雷です。
ありがちな会話
上司「とりあえずこの企画、俺のやり方でやってみて」
部下「(背景も説明なく、やり方だけ?)」
失敗例A:初月から「レビューは全部俺がやる」と抱え込み、ボトルネック化。部下の成長機会も奪い、不満が溜まる。
失敗例B:逆に“優しさ”が過剰で意思決定を先送り。「結局どっち?」と聞かれ、信頼が落ちる。
成功例:初回1on1で期待役割・裁量範囲・アウトプット基準を合意。レビューは「型を渡す→任せる→最後に整える」の三段階で徐々に手を離す。
回避策ToDo
- 入社2週間以内に1on1全員実施(期待・裁量・評価の擦り合わせ)
- 会議では結論→理由→期限の順に話す(曖昧さを残さない)
- 「任せる」は観察とフィードバックとセットにする
3. スキルのアップデートを止めている
40代は経験で戦える半面、「新ツールが苦手」「最新トレンドが追えていない」が表面化しやすい。周囲は口に出さないけれど、“学ばない上司”は一瞬で見抜かれます。
失敗例A:社内SaaSの操作を部下に丸投げ。「俺は口を出す側」に徹して自ら学ばず、判断が遅れる。
失敗例B:業界ニュースを追わず、過去の常識で意思決定。提案がズレて採択されない。
成功例:入社初月に社内研修・ベンダー資料・社外セミナーを自腹でも受講。自分でダッシュボードを触り、週1で学びをチーム共有。「学ぶ姿勢」が信頼を生む。
回避策ToDo
- 30日で社内システムの“使える”レベルへ(ID発行→触る→メモ)
- 毎朝10分の業界ニュース3本インプット→金曜にSlackで要点共有
- 四半期に1回、外部セミナー登壇/参加で外の空気に触れる
4. 成果を急ぎすぎる
「早く結果を出さなきゃ」で突っ走ると、根回し不足で敵を増やすだけ。組織は論理だけで動きません。
失敗例A:大型プロジェクトを“正論”で押し切るが、関係部署が動かず頓挫。
失敗例B:現状否定から入って反発を招き、協力者ゼロに。
成功例:最初の90日は人と課題の地図づくり。誰が何に困っていて、どの利益を守っているかを把握。3か月後に小さく勝つ案件を作り、反対派も巻き込む。
回避策ToDo
- 30人ヒアリング(上長/同僚/現場/他部門)で利害関係マップを作る
- まずは低リスク高インパクトの改善で信用を稼ぐ
- “正しさ”より一緒にやりたい空気を先に作る
5. 「過去の肩書き」で仕事をしようとする
前職の実績は誇っていい。でも、今の会社ではまだ実績ゼロ。肩書きの威光で進めようとすると、反発を生みます。
失敗例A:「前は部長だったから」で意思決定を急がせ、不信感を買う。
失敗例B:成功体験を盾に部下の提案を否定。イノベーションの芽を摘んでしまう。
成功例:最初の四半期は**“現職での小さな勝ち”**だけを語る。数字とお客さまの声で信頼を積み、半年後に権限が自然と集まる。
回避策ToDo
- 週1で今週の小さな勝ちを可視化(数値・学び・次の一手)
- 会議での自分の発話比率を5割以下に抑える(聴く時間を増やす)
- 「過去話」は月1本の学び記事として社内共有に封じ込める
実際に見た“消えていった/残った”分岐
- A氏(消えた):入社直後に改革宣言→根回し不足→摩擦→半年で異動。
- B氏(残った):3か月観察→小さく改善→他部署と共催で成果→1年で部門横断の役割に昇格。
- C氏(消えた):部下を信じきれず抱え込み→疲弊→評価ダウン→退職。
- D氏(残った):任せる設計に振り切り、レビューは“型”で支援→チームが自走し自分は先回りに専念。
90日アクションプラン
Day 0–30:観察と地図づくり
- 1on1全員、関係部署は計30人ヒアリング
- 現行KPI/業務フロー/意思決定ルールを図解化
- 社内SaaS/ダッシュボードは自分の手で触る
Day 31–60:小さく勝つ
- 低コストの改善(例:レポート自動化、朝会10分短縮)で“効く”を実証
- 週1の学び共有、月1の部内LTで学ぶ文化を見せる
Day 61–90:巻き込みと標準化
- 成功パターンをチェックリスト化→他チームと共催導入
- 反対派の懸念を先に吸い上げ、設計に反映
- 次四半期に向けた中型プロジェクトを宣言
まとめチェックリスト
- 「前職では」を封印し、観察→小さな検証の順で動いている
- 1on1で期待・裁量・評価をすり合わせた
- 新ツール/トレンドの自習時間を確保している
- 成果より味方づくりを先にやっている
- 過去の肩書きではなく、今ここでの成果を語っている
よくあるQ&A
Q. 何から直せばいい?
A. まずは「前職比較の封印」と「1on1の即実施」。これだけで初期の摩擦が半分になります。
Q. 成果を出せと言われているのに、観察に時間を使って大丈夫?
A. 観察は“成果への最短ルート”です。外してやり直す時間のほうがコスト高。最初の30日は地図づくりに投資しましょう。
Q. 部下が年上でやりづらい
A. 役割の違いに立ち返り、期待値・裁量・期限を明文化。敬意を払いながらも、意思決定は曖昧にしないのがコツです。
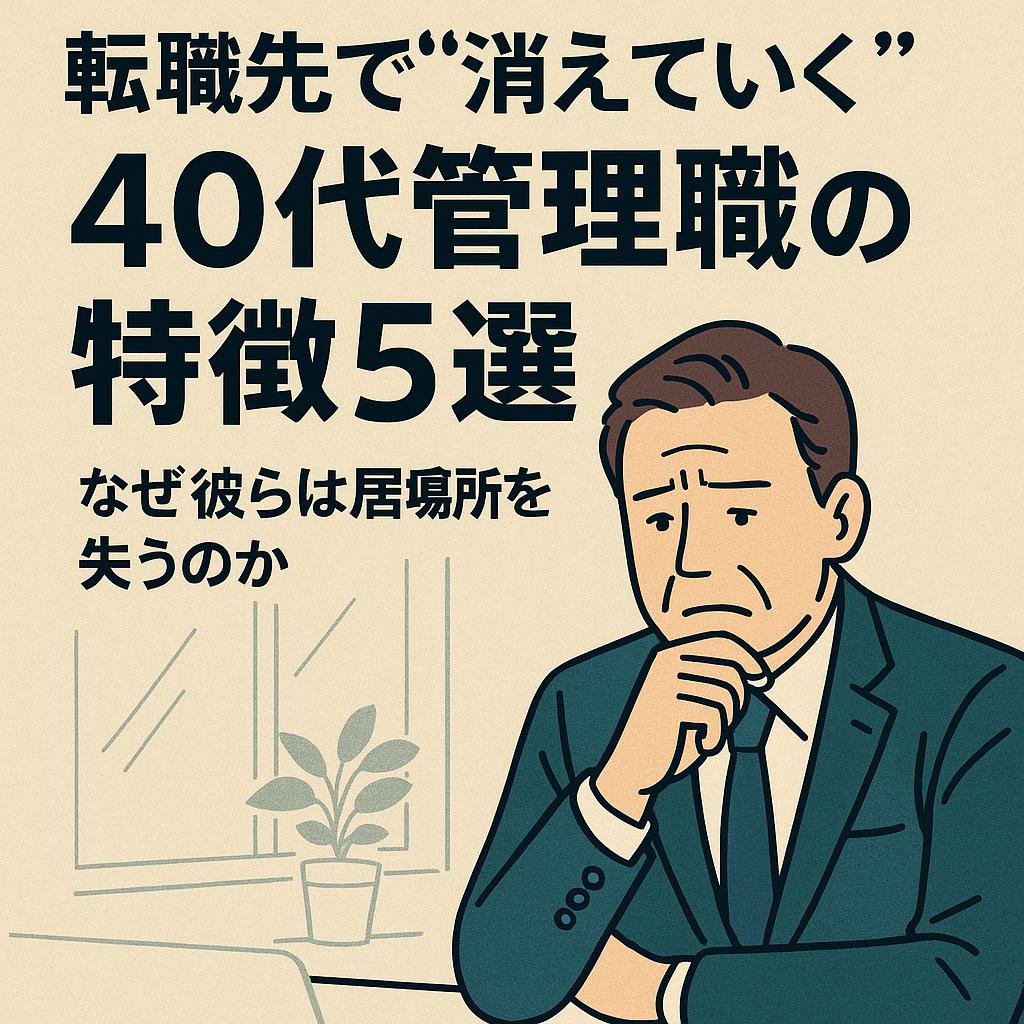


コメント